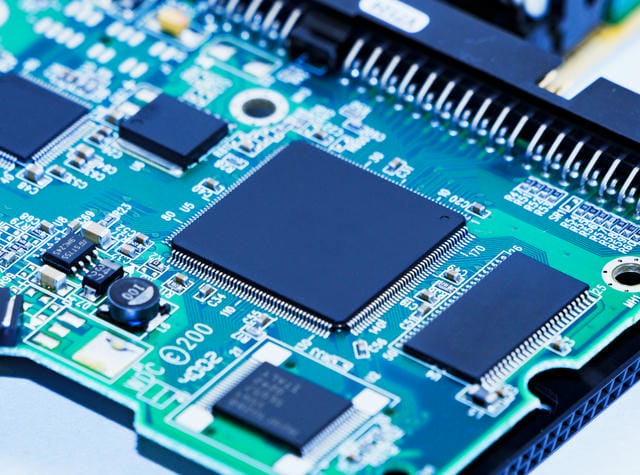エンドポイントセキュリティの新時代EDRとは脅威に先回りする次世代防御策

企業や団体が情報環境を維持し、業務を安全に継続するうえで重要となるのが、サイバー攻撃や不正アクセスからの防御手段である。情報セキュリティの世界では様々な用語や技術が登場するが、その一つが端末に対する有効な保護の方法である。これまで情報セキュリティといえば、パソコンやサーバーにウイルス対策ソフトをインストールし、ネットワークの入口出口を監視するファイアウォールや侵入検知装置などで防御することが中心とされてきた。しかし、近年はマルウェアや標的型攻撃の手口が巧妙化し、従来の対策だけでは十分な防御が難しくなっている。その背景にはゼロデイ攻撃など未知の脅威が存在し、署名ベースのウイルス検知だけでは正確な把握が困難で、実際の被害発生後の対応も煩雑になるという課題がある。
そこで注目されるのが、端末の挙動に着目し、リアルタイムで脅威検出と対策を可能とする仕組みである。この仕組みは、サーバーやパソコン、ノートパソコンをはじめとするエンドポイントという位置付けの端末で、実行中のプロセス、メモリ、ファイル操作、ネットワーク通信の内容などを詳細に監視、記録する。そして管理者は専用の管理画面から、端末で発生したイベントを一覧で把握し、疑わしい動作を早期に検出して隔離、駆除まで行うことができる。多くの場合、こうしたセキュリティ製品はエンドポイントの挙動監視ソフトと、専用のサーバーを中核とした管理基盤で構成されている。端末監視用のソフトウェアは、それぞれのパソコンやサーバーごとにインストールされ、端末内部で動作するプログラムの振る舞い、ファイルの変更履歴、ネットワーク上の通信パターンを解析して、不審な兆候があれば、その内容を記録する。
管理基盤となるサーバー側では、すべてのエンドポイントから送信された膨大なログデータを集約、解析し、既存の情報と照合して、脅威とみなされる挙動を発見する。場合によっては、外部の脅威情報データベースと連携し、世界で発生している最新の攻撃手口を反映させることも少なくない。こうした一連の仕組みにより、未知の攻撃や内部犯行、標的型の攻撃にも迅速に対応できるようになる。端末上で管理画面にて検知したイベントを詳細にたどれるため、マルウェアがどの経路で侵入し、どのプロセスから感染拡大につながったか、その流れを可視化できるのが特長である。これにより万一攻撃を受けた場合でも、感染範囲の特定、影響範囲の評価を迅速に進めることができる。
さらにはインシデント対応として、問題のある端末をネットワークから即座に遮断する隔離機能や、管理者が遠隔でのファイル削除といった対応を施せる機能も持つ。このような仕組みが導入された場合、サーバーやネットワークとの連携は不可欠である。例えば、大規模組織で数百、数千台単位のエンドポイントを一元的に管理するには、中央のサーバーが各端末と通信し、データや設定を配信・収集する必要がある。また、ネットワーク機器やサーバーとの相互連携によって、検知した脅威の拡大防止策をリアルタイムで実施するなど、複数レイヤーでの防御を実現できる。このような総合的なセキュリティ体制の実現には、単なる端末監視にとどまらず、ネットワーク、サーバー、運用面など様々な要素が複合的に作用する。
多くの導入現場の知見として、運用時に留意しなければならないのは、端末から発信される膨大な監視データ、イベントログをサーバー側で効率的に処理できる体制の整備である。特に不審な挙動が多発した場合や、多数のアラートが発生した場合、本当に深刻な脅威をどのように特定するか、その運用ルール策定と管理者の負担軽減は重要なポイントとなる。対策として、アラートの自動整理や脅威スコアリングなど、管理者の手作業を減らす工夫が取り入れられている。サイバー攻撃者が組織内のネットワークに侵入を試みた際の初動から、不正なプログラムの検知、その挙動から更なる感染拡大をブロックするまでの一連の流れをシームレスに監視、トレースできるこの仕組みは、単なる防御に限定されない。情報漏洩や内部不正対策、端末資産管理やソフトウェア更新の一元化といった、運用全体の効率化と安全性向上にも活用できる点が注目されている。
特にリモートワークや分散拠点が普及する社会環境では、本社ネットワークと直接物理的に接続できない端末の安全も包括的にカバーできる利点が大きい。今後もサイバー攻撃の多様化、高度化が進む中で、ネットワーク全体を監視するのみならず、エンドポイント、サーバーごとにきめ細やかなトレースとリアクションが必須となる。この種の対策は、単にセキュリティ部門だけで完結するものではなく、全社的なポリシー策定と継続的な運用の見直し、従業員意識の醸成まで必要となる。状況に即した柔軟な計画と最新技術の取り入れを欠かさず、脅威が現実化する前に多層的に防御するという考え方が、これからの情報社会を支えていく道筋となる。企業や団体の情報セキュリティ対策として、従来はウイルス対策ソフトやファイアウォールなどによる防御が主流だったが、標的型攻撃やゼロデイ攻撃といった巧妙な手口の増加により、これだけでは十分な防御が難しくなってきた。
こうした中、エンドポイント、すなわちパソコンやサーバーなど端末自体の挙動を詳細に監視し、リアルタイムで脅威を検出・対処できる技術が注目されている。この仕組みは端末内部のプロセスやファイル操作、ネットワーク通信などを監視し、不審な挙動を管理基盤へ報告・記録し、管理者が端末の状態を可視化できる。さらに、感染範囲の特定や影響評価、ネットワーク隔離など迅速なインシデント対応を可能とし、サーバーやネットワークとの連携による多重防御も実現されている。大規模な組織では、多数の端末から集約される大量の監視データの効率的な管理や、アラートの自動整理といった運用上の工夫が求められる。単なる防御に留まらず、資産管理やソフトウェア更新の一元化、またリモートワーク環境における端末の安全確保など、情報管理全体の効率化と強化にも貢献する。
今後は、全社的なポリシーと柔軟な運用、従業員の意識向上を含め、多層的かつ継続的な防御姿勢が重要となる。